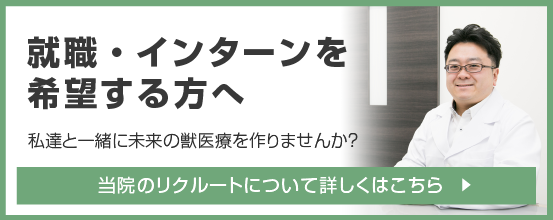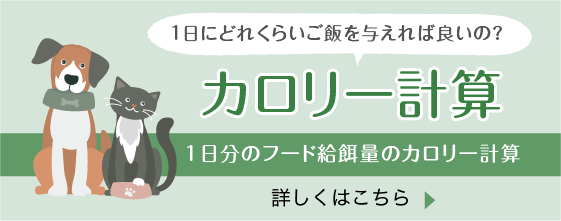犬猫の避妊手術をするにはどうしたらいい?当院での流れをご案内します
皆さんは「避妊手術」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。避妊手術は、一般的に女の子に対する繁殖をできなくする手術を指します。
多くの犬や猫にとって生まれて最初に経験する手術であり、うちの子も経験した!と思われる方や、検討している方も少なくはないはずです。
今回は、そんな避妊手術のメリットやデメリット、当院で避妊手術を受ける際の流れについて解説していきます。
避妊手術のメリット、デメリット
<メリット>
・病気の予防
避妊手術を行うことで防ぐことのできる病気がいくつか存在します。
例えば、未避妊の犬猫で多く報告されているものの一つに子宮蓄膿症があります。これは、子宮に膿が溜まる疾患です。
元気や食欲の低下、陰部から膿や出血がみられるなどの症状が多くみられますが、命に関わる場合もあります。避妊手術を行うことで、生涯発症の可能性をなくすことができます。
子宮蓄膿症について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
また、乳腺腫瘍も未避妊の犬猫で多く報告されている病気です。
避妊手術を初回発情前に行うことで、犬で99%以上、猫でも90%以上の割合で乳腺腫瘍を予防できるといわれています。
 |
 |
乳腺腫瘍について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
他にも雌性ホルモンが関与する疾患として膣過形成や膣脱、未避妊の犬でみられる偽妊娠などが挙げられます。これらの疾患は、避妊手術によってその発症リスクを大幅に抑えることができると考えられています。
・性行動の消失
避妊手術を行うことで、性的な異性に対する興味が消失します。精神的な安定が得られるようになると、性ホルモンに関連する問題行動の抑制も期待できます。
ただし行動面に関しては、手術を行うだけでなく基本的なしつけやその子にあった接し方がとても重要となります。
・望まれない妊娠を防ぐ
避妊手術をしていない場合、想定外の交配で子犬子猫が増えてしまうことがあります。責任を持った飼育のためにも、適切な時期に避妊手術を行うことをお勧めします。
<デメリット>
・子孫を残せない
避妊手術は子宮や卵巣を取り除く手術であり、当然一度取り除いた臓器は元には戻せません。
ご自宅での繁殖はさまざまな知識や労力が必要となりますので安易に勧められませんが、将来設計についてご家族全員でよく話し合った上で手術を実施しましょう。
・全身麻酔の必要性
避妊手術は全身麻酔下での手術となります。麻酔中は心電図モニターなどを使いしっかりと状態を確認しながら行いますが、100%安全というものでもありません。
若齢での避妊手術では合併症が起こることは非常に少なくなりましたが、起こり得ることとしては不整脈、徐脈、体温や血圧の低下、投与した薬剤へのアレルギー反応などが挙げられます。
一部の症例では心停止のリスクを伴うものでもあります。しかし、手術は人間同様、動物の体にとっても痛みや体に負荷のかかるものであるため、しっかりと麻酔をかけて実施する必要があります。
・太りやすくなる
ホルモンバランスが変化することによって一日の代謝エネルギー量が減り、太りやすくなります。
体重が増えすぎるとかかりやすい病気も存在するので、避妊手術後は特に食事量や運動の管理を行っていきましょう。
食事量に関して、当院HPで1日に必要なカロリーから計算することができます。ぜひ活用してみてくださいね。食事に関しては、こちらの記事でもご紹介しておりますのでご覧ください。
避妊手術についてのメリット、デメリットについて詳しくはこちらの記事もご覧ください。
避妊手術のタイミング
「避妊手術は必ず何歳までに終わらせておきましょう」という制限はありません。
獣医療の様々なガイドラインを策定している海外の機関の発表によると、成犬時体重が20kgに満たない犬の場合は初回発情前である5,6カ月齢での手術を推奨しています。
20kgを超える犬では獣医師とタイミングをよく相談していくようにしましょう。これは、大型犬の場合早すぎる手術は関節疾患の発症の可能性があるとされているためです。
猫の場合は、初回発情前である5カ月齢が理想的とされています。しかし、動物の避妊去勢手術の適齢期に関する研究は多くなく、国によって違いがあるのが現状です。
また、もしも手術時に発情を迎えてしまった場合には、出血が多くなる可能性があることから手術の予定を延期するようご提案させていただく場合があります。
また、生後5カ月齢ころから、永久歯が生えてきます。通常、永久歯が生えて数日から2週間くらいで乳歯は抜けますが、抜けずに残る場合もあります。これを乳歯遺残といい、特にチワワやトイプードルなどの小型犬は骨格などの遺伝的素因から多くみられる傾向があります。
抜けずに残った乳歯は咬み合わせが悪くなる(不正咬合)、歯垢が溜まりやすく歯周病の原因にもなり得ることから抜歯を行う必要があります。当院では、乳歯の生え代わりの様子を見ながら、自然に抜けていない乳歯は避妊手術時に抜歯を行っています。
当院の手術プラン
当院では、「スタンダードプラン」と「プレミアムプラン」のどちらかをお選びいただけます。それぞれのプランによって、手術の方法が異なります。
まずスタンダードプランでは、糸によって血管を縛り、子宮と卵巣を摘出します。
一方プレミアムプランは、糸を使わず血管シーリングデバイスという機械を用いて子宮と卵巣を摘出します。これにより、糸で縛る分の手術時間の短縮や、稀に生じる縫合糸への生体反応を予防することができます。
ただし、どちらのプランでもお腹を閉じる際や、皮膚を縫合する際には縫合糸を使用します。皮膚を縫合する糸は抜糸を行うので、最終的にずっと残り続ける糸はありません。
手術プランに関しては、診察や身体検査を行う中でその子に合ったプランをご提案させていただく場合もあります。
当院での手術の流れ
避妊手術は全身麻酔での手術となります。全身麻酔をかける上で問題がないか調べるために、手術の約1週間前に術前検査を行います。
検査の内容としては、血球検査・血液化学検査のほかにプレミアムプランをお選びいただいた場合には門脈体循環シャントなどの天性疾患のスクリーニングができる総胆汁酸検査、止血機能に問題がないか検査する血液凝固系の検査も術前検査として追加します。また、その他に動物の状態によって必要な検査を追加する場合もあります。これらの検査は8時間以上の絶食の状態で行っています。
手術を行う上で問題となる異常がなければ、予定通りの日程で手術を実施します。手術中や術後、健康状態に問題がなければ、翌日の退院が可能です。退院時には術創の保護のために、エリザベスカラーまたは術後服を着用していただきます。
エリザベスカラーや術後服に関して詳しくはこちらの記事をご覧ください。
退院翌日、当院ではご様子確認のためのご連絡をいたします。ご自宅にお帰りになられてからのご様子や術創を気にしていないかなどについてお話を伺い、必要に応じて診察のご案内をいたします。抜糸をするまでの間は、いつも通りお散歩をしていただいて問題ございません。
手術から10~14日後に、再診察と抜糸を行います。
当院では、避妊手術相談としての診察も承っております。手術や入院、退院後の管理に関してご不安な点などがございましたら当院スタッフまでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人